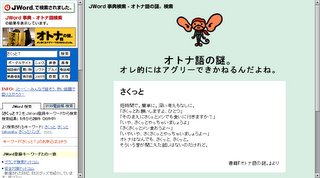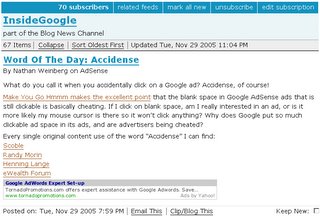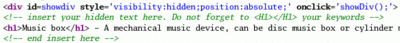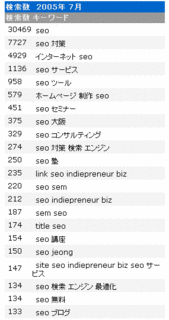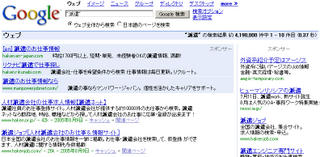"従来型のSEO だけのサービスでは半年契約で五十万円程度。"……月額の間違いだろうか。そうであると信じたい。半年50万円では2002年頃のプライスに逆戻りだ。
 まあ別に、ターゲットとする企業の規模によってはそういう価格設定もアリだろう。しかし、このSEM 会社の場合は違うような気が。記事に書かれている内容を本気で実践して、その値段でどうして工数割れしないのか、不思議でしかたがない。価格破壊というより品質破壊と呼ぶべきだろうか。
まあ別に、ターゲットとする企業の規模によってはそういう価格設定もアリだろう。しかし、このSEM 会社の場合は違うような気が。記事に書かれている内容を本気で実践して、その値段でどうして工数割れしないのか、不思議でしかたがない。価格破壊というより品質破壊と呼ぶべきだろうか。……気分が乗ってきたのでもう少しばかり。いわゆる「成果報酬型のSEO」なる謳い文句を目にすることが増えた。導入前に双方で取り決めた順位まで上昇した時点から、順位の変動に応じて月々の費用が発生する、というタイプのSEO らしい。企業側では、成果が出るまで支払いを行う必要がなく、発注しやすいということで歓迎する向きもあるようだ。
しかし実のところ、「成果報酬型」と「SEO」は相性が悪い。
SEO の日本語訳「検索エンジン最適化」とは、「検索エンジンに適切に評価されるよう、自サイト内外の状態を最適化すること」。実際にサイト内の構造やページ記述から、サイト外からのリンクの形まで最適化が行われ、ページの主題となるキーワードで上位に表示されると、(それこそGoogle 八分にでもあわない限り)しばらくはその順位がキープされてゆくことがほとんどだ。
となれば、成果報酬型のSEO サービスに対して「契約期間終了(もしくは破棄)後も上位に表示されつづけたら業者側が損をするのではないか」という疑問がわく。しかし実際には、契約終了後しばらくすると急激に順位が下降する(らしい)。これには当然からくりがあって、このタイプの業者は自分たちで制御可能な要因、つまり自社で保有するサイトやリンク集から、キーワードを含んだ大量のリンクをクライアントのサイトへ発生させているだけなのだそうだ(と伝聞調)。
これは本当にSEO の名に値するものなのだろうか。けっこうな費用を払ってもクライアント側には何のノウハウも残らず、契約終了とともに強力な外部リンクも撤去される。残るのは順位の下がった自社のサイトだけ。……ぼちぼち考え直す次期に来ているのではないだろうか? クライアントも、SEO 会社も。